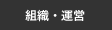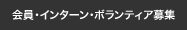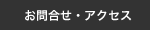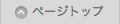東ティモール報告・独立の光と影
上杉勇司 / Yuji Uesugi 沖縄平和協力センター事務局長
独立の光と影
11月8日から18日まで東ティモールを訪れた。私の東ティモール訪問は、今回で3度目になる。最初は、独立前の2001年8月に、国連の暫定統治下で実施された制憲議会選挙を監視するため、2回目は2002年4月に大統領選挙を監視するために訪問した。また、2002年11月に東ティモールの青年団20名を沖縄で受け入れた際には、その調整を担当した。今回の訪問の目的は、東ティモールの復興を支援するといった場合に、沖縄から何ができるのかを考えることにあった。国づくりに励む東ティモールの実情を把握するために、現地を訪れ、グスマン大統領や昨年に受け入れた青年たちなど、国づくりの担い手たちに話を聞いた。
東ティモールは、約20年に及ぶ内戦や独立闘争に終止符を打ち、2002年5月20日に独立を果たし、ようやく国づくりの第一歩を踏み出したところである。東ティモールの将来を決めた1999年の住民投票の前後に国際社会の脚光を浴びたことが嘘のように、今では国際社会の関心は薄れ、世界の目は、アフガニスタンやイラクへと移ってしまった。ゼロからの復興という前途多難な航海にサバニ一艘で漕ぎ出したかのような東ティモールではあるが、その存在を忘れてしまうのではなく、友人として温かく見守り続けていくことが大切であると考え、今回、東ティモールの現状をレポートすることにした。
1年半ぶりの東ティモールで、まず目に飛び込んできたものは独立の「光」の部分であった。市場には物が溢れ、人々の表情は明るく、身に着けている洋服もきれいになった。車や新しい建物も増えた。子供たちの笑顔も相変わらず最高だ。人々ディリ市内のマーケットにては、自由を謳歌しているようであった。
しかし、東ティモールの数年先を見据えて国づくりに取り組むリーダーたちに話を聞くと、東ティモールが抱える問題の深刻さ、独立の「影」の部分が見えてきた。とりわけ今まで抵抗運動に参加してきた元ゲリラ兵の処遇をめぐる問題が、独立を期に懸案事項として浮かび上がった。元ゲリラ兵の中には、定員1,500名の国防軍に編入された者もいたが、確認されているだけで3万5千名あまりが、恩給や生活保障もないまま地域社会に放り出される格好となった。
この問題は、潜在的な社会不安の要因になりかねないとして、東ティモール政府としても、労働・連帯省の退役軍人局を中心に対策にのりだし、現在は元ゲリラ兵の登録・認定作業を進めているところであった。他方、国際機関も国際移住機関や国連開発計画などが元ゲリラ兵の支援事業を展開している。国連開発計画の事業は「リスペクト」と呼ばれ、農業開発、地域社会のインフラ整備、職業訓練などの重点分野における雇用創出に主眼を置いたもので、基本的には灌漑設備の建設や橋梁の補修などに元ゲリラ兵を雇用し、彼らの不満が鬱積することを防ぐことを目的としている。
ところで、このリスペクトには、東ティモールで復興支援にあたっている自衛隊も国連PKOの民生支援の枠組みで協力していた。例えば、自衛隊が指導員となって、東ティモール人の工事監督者に対する管理業務の指導を行ったり、重機の運転や整備の方法を指導したりしていた。ただし、自衛隊の主要な任務は幹線補給路の補修整備であり、民生支援はあくまでも主要な業務に支障がない範囲で実施されている。加えて自衛隊は来年の5月には東ティモールから撤退するため、NGOなどの他の組織がフォローアップしていく必要があるだろう。
リスペクトの一環として、来年の撤退を控え自衛隊の駐屯地の跡地を利用して、平和公園を建設する構想がある。実は今回の滞在中に、グスマン大統領と学生があふれるディリ市内の学校平和公園の構想について意見を交わす機会があった。その際に、敵味方の違いを乗り越えて、紛争のすべての犠牲者を追悼する沖縄の「平和の礎」の理念を説明し、東ティモールの平和公園にも取り入れることを提案した。東ティモールの安定と繁栄のためには隣国インドネシアとの和解が大切であると説く大統領は、この提案に関心を示したものの、現実にはインドネシア軍側の犠牲者をも含めた記念碑の設置に心情的な難しさがあることを指摘した。その代わりに大統領からは、平和公園への植樹についての提案があった。大統領の構想は、平和公園を東ティモールの県の数だけ区画分けして、そこへ各県の代表的な花木を植樹するというもので、大統領の提案は、その一画に「沖縄区」を設けるので、そこへ沖縄から花木を送ってくれないかというものであった。折しも、11月21日には沖縄平和賞の関連事業として「花の平和交流事業」が実施され、沖縄からカンボジアへ千本あまりの花木が送られ、植樹式には百五十名ちかくの沖縄県民が参加している。
今後、東ティモールに対する国際社会の関心はますます薄れていくと思われるが、私たちは東ティモールを忘れることなく、引き続き友人として協力していきたい。そして、いかなる形でも良いが、沖縄と東ティモールの友好の架け橋を築いていれたらと思う。
(本文は琉球新報2003年12月18日に掲載されました)